
大手チェーン店などの眼鏡はなぜ安いのか理由が気になっている方も多いのではないでしょうか。最近では、ZoffやJINSをはじめとする格安眼鏡チェーンが人気を集め、安価で手軽に眼鏡を購入できる時代になりました。しかし一方で「なぜそんなに安いのか」「本当に大丈夫なのか」と疑問に思う人もいるでしょう。
本記事では、チェーン店などの眼鏡が安い理由を詳しく解説しつつ、高い眼鏡との違いや、価格だけで選ばないための正しい眼鏡の選び方についても紹介します。価格だけでなく、品質やサービス、フィッティングの重要性まで含めて、納得して眼鏡を選びたい人必見の内容です。
- チェーン店などの眼鏡が安い理由とその仕組みがわかる
- 安い眼鏡と高い眼鏡の品質やサービスの違いが理解できる
- 価格だけで選ばない、後悔しない眼鏡選びのポイントがわかる
- 自分に合った眼鏡を選ぶための基準と注意点がわかる
もくじ
チェーン店の眼鏡が安い理由とは?:安さの秘密
- 眼鏡の平均価格と価格帯
- 高い眼鏡店と安い眼鏡店の違い:品質と製造
- 高い眼鏡店と安い眼鏡店の違い:サービスと販売
- Zoff、JINSなどの格安眼鏡チェーンとその他の眼鏡店の違い
- 産地とブランドによる価格の違い
- レンズの種類と価格差
眼鏡の平均価格と価格帯

眼鏡を新しく購入する際、まず気になるのがその価格ではないでしょうか。近年、眼鏡の価格は以前と比べて手ごろになり、より購入しやすい環境が整っています。2024年5月時点における眼鏡の平均価格は約28,220円です。この数字は、2016年当時の約21,000円(単焦点レンズとフレームのセット)と比べるとやや上がっていますが、それでも手の届きやすい価格帯の眼鏡が増えてきていることがわかります。
ただし、実際の価格帯は非常に幅広く、1万円以下で購入できるものから、2万円台、3万円台の製品、さらに10万円を超える高級眼鏡まで存在しています。また、価格はレンズの種類によっても大きく異なります。例えば、単焦点レンズと比べると遠近両用眼鏡に使われる累進レンズは高額になり、相場はおおよそ2万円から6万円台に達することも珍しくありません。
眼鏡市場のような大手チェーンでは、フレームとレンズを合わせた一式価格が税込13,200円から提供されています。しかも、この価格帯で単焦点レンズだけでなく、遠近両用や超薄型レンズといったレンズも選べる場合があり、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢といえるでしょう。
このように、眼鏡の価格はお店や選ぶレンズの種類によって大きく変わるため、購入する際は自分の予算や必要とする機能、デザインなどを総合的に考慮して選ぶことが大切です。
高い眼鏡店と安い眼鏡店の違い:品質と製造
眼鏡の価格差が生まれる大きな理由の一つが、フレームやレンズの素材、そしてその製造方法にあります。安い眼鏡と高い眼鏡では、使われている素材から製造の工程、仕上がりまで大きな違いがあります。
フレーム素材と製造方法
安い眼鏡店で扱われるフレームは、主にポリアミド、ウルテム、TR90といった石油由来の樹脂素材が使われています。これらの素材は軽くて弾力性があり、温度変化にも強いという特徴があります。しかし、インジェクション成形やプレス成形といった大量生産向けの方法で作られるためコストを抑えられる一方、細かい調整が難しかったり、曲げにくいという欠点もあります。また、使われているヒンジなどの部品も簡易的なものが多く、耐久性に劣る場合があります。長く使っているうちにメッキが剥がれたり、素材自体が劣化することも少なくありません。
一方で、高い眼鏡店で扱われるフレームには、アセテートやセルロイドといった天然素材や、チタンなどの高品質な金属素材が使われています。アセテートは透明感や独特の光沢があり、カラーバリエーションも豊富で、熱を加えることで細かいフィッティング調整が可能です。セルロイドは昔から使われてきた素材で独自の風合いがありますが、可燃性の高さから取り扱うブランドは減っています。金属フレームの代表的な素材であるチタンは、軽量で錆びにくく、金属疲労やアレルギーも起きにくい優れた素材ですが、加工が非常に難しく、製造には高度な技術が必要です。
高級な金属フレームは、常温で何度もプレスを繰り返すなど時間と手間のかかる工程を経て作られています。そのため、強度と耐久性に優れており、ヒンジも埋め込み式のしっかりした作りで、長く使っても開閉がスムーズです。また、フレームの表面は職人の手作業によって磨き上げられ、滑らかで美しいラインと光沢が生まれます。このような工程が、見た目だけでなく、長期間使用できる耐久性にもつながっています。
レンズの品質
レンズも、安い眼鏡店と高い眼鏡店では大きな違いがあります。安い眼鏡店で使われるレンズは、海外の工場で大量に生産されていることが多く、コストを抑えられているのが特徴です。視力矯正という基本的な役割は果たしますが、レンズの歪みが出やすかったり、表面のコーティングが傷つきやすい場合があります。傷防止や汚れ防止、反射防止といったコーティングの質も、高価なレンズと比べると簡易的なものが多く、使っていくうちに不満を感じることがあるかもしれません。
それに対して、高い眼鏡店で取り扱うレンズは、素材の質が高く、多層コーティングによって傷や汚れがつきにくくなっています。また、視界の歪みが少なく、クリアで自然な見え方を提供するために、非球面設計や特殊な光学技術が用いられています。さらに、ユーザー一人ひとりの目の状態やライフスタイルに合わせたオーダーメイドレンズが選べることもあります。
ブランドによっては、乱視矯正に特化した設計や、ピント合わせがスムーズにできるよう工夫されたレンズ、ブルーライトカットや紫外線カットといった目を守るための機能を持つレンズも展開されています。こうした高品質レンズは、長時間装用しても疲れにくく、クリアな視界を長く維持できるのが特徴です。
このように、フレームとレンズそれぞれの素材や製造方法、品質の違いが、眼鏡の価格差を生み出す大きな理由となっています。価格だけで判断するのではなく、自分の使用目的や重視したいポイントを考えたうえで、どのクラスの眼鏡が合っているのかを見極めることが大切です。
高い眼鏡店と安い眼鏡店の違い:サービスと販売
眼鏡の価格差は、製品そのものの品質や製造方法だけでなく、購入時や購入後に提供されるサービスや対応にも大きく関わっています。安い眼鏡店と高い眼鏡店では、視力測定やフィッティング、アフターサービスにおいても大きな違いがあります。
視力測定
安い眼鏡店では、短時間で効率的な視力測定が行われることが一般的です。コスト削減のため、アルバイトスタッフが視力測定を担当する場合もあり、必ずしも専門的な知識や経験が十分でないこともあります。そのため、測定の精度が十分に確保されないことがあり、度数が合わない眼鏡になってしまうリスクも考えられます。
一方で、高い眼鏡店では、視力測定に時間をかけ、丁寧なヒアリングや問診を行いながら顧客のライフスタイルや目の使い方まで把握したうえで度数を決定することを重視しています。国家資格である一級眼鏡作製技能士など、専門知識を持つスタッフが対応することが多く、正確な視力測定と目の状態の詳細な分析を通じて、一人ひとりに最適な度数を提案しています。また、必要に応じて眼科の受診を勧める場合もあり、医師による処方箋に基づいた眼鏡の作製が推奨されることもあります。
フィッティング
フィッティングについても、安い眼鏡店と高い眼鏡店では大きな違いがあります。安い眼鏡店では、フレームの素材や構造が安価なものであることが多く、柔軟性に欠ける場合があります。そのため、顔の形に合わせた細かい調整が難しく、効率を重視してフィッティングが簡略化される傾向もあります。
一方、高い眼鏡店では、フレーム素材やデザインにこだわっており、顔の形や瞳の位置に合わせたミリ単位の繊細な調整が行われます。適切なフィッティングは、掛け心地の良さだけでなく、レンズの中心と瞳の位置を正確に合わせることで視界の質を高めるうえでも非常に重要です。このため、フィッティングの技術がしっかりしている眼鏡店ほど、長時間快適に使える眼鏡を提供できるのです。
アフターサービス
購入後のアフターサービスにも違いがあります。安い眼鏡店では、基本的なアフターサービスが限定的な場合が多く、フレームの調整や修理が有料となることもあります。ネジの緩みやレンズを支えるナイロール糸の交換など、通常のメンテナンス対応が十分でない場合も考えられます。また、製品が店頭に並ぶ前の検品も、度数やレンズ中心の位置など最低限の項目だけにとどまることがあり、仕上がりの精度にばらつきが出ることもあります。
これに対して、高い眼鏡店では購入後のサポートが充実しており、フレームの再調整、ネジの締め直し、修理対応、保証サービスなどがしっかり提供されます。定期的なメンテナンスも無料で対応する場合があり、長く安心して使えるよう配慮されています。また、販売前の検品も細かく行われ、見え方や仕上がりに問題がないことを確認したうえで顧客に渡されるため、信頼性が高いのも特徴です。
このように、視力測定、フィッティング、アフターサービスといった一連の対応の質が、眼鏡の価格差に反映されています。単に価格の安さだけで選ぶのではなく、どこまで丁寧なサービスが受けられるのかという点も含めて、購入する眼鏡店を選ぶことが重要です。
Zoff、JINSなどの格安眼鏡チェーンとその他の眼鏡店の違い
眼鏡が安く提供される背景には、店舗ごとのビジネスモデルやサービス体制の違いがあります。ここでは、ZoffやJINSなどの格安眼鏡チェーンと、その他の眼鏡店の違いについて詳しく見ていきます。
販売店のビジネスモデル
ZoffやJINSといった格安眼鏡チェーンは、SPA(製造小売)というビジネスモデルを採用しています。これは、フレームの企画から製造、販売までをすべて自社で一貫して行うことで、流通コストや中間マージンを削減し、低価格を実現する仕組みです。これらの店舗では、自社オリジナルのフレームのみを取り扱っており、レンズもコストを抑えた低価格帯の製品が採用されていることがあります。また、双眼鏡やルーペなどの関連商品を扱わず、眼鏡に特化することで在庫管理のコストを削減し、さらに効率的な店舗運営を進めています。
一方、眼鏡市場のような量販店では、比較的手ごろな価格帯の商品を幅広く取り揃えており、格安眼鏡店よりも価格はやや高めに設定されている場合があります。しかし、眼鏡市場の特徴は、フレームとレンズを一式価格で販売し、その中に視力測定やレンズ加工費も含まれていることです。専門店である眼鏡ストアーやパリミキなどでは、さらに専門的な知識と技術を持つスタッフが常駐し、丁寧な視力測定やフィッティング、アフターサービスを行っていますが、その分価格も高めになる傾向があります。
また、個人経営の眼鏡店では、店主独自のこだわりやセレクトによるフレーム展開、個別対応が特徴であり、価格はお店によって異なります。オンライン販売も広がりを見せていますが、手軽に購入できる一方で、実際に試着やフィッティングができないため、調整が難しいという課題もあります。さらに、オンラインでは自分で度数を指定しなければならず、度が合わないリスクや、アフターサービスが受けにくいといったデメリットもあります。おしゃれ目的で度なしレンズを楽しむ場合はオンラインでも良いかもしれませんが、視力矯正を目的とする処方箋付き眼鏡については、専門店での購入が安心だといえるでしょう。
従業員の知識と技術
格安眼鏡チェーンとその他の眼鏡店では、従業員の教育や技術にも大きな違いがあります。ZoffやJINSなどの格安チェーンでは、人件費削減のためアルバイトスタッフが中心となる場合が多く、必ずしも高度な専門知識や技術を持つスタッフばかりではありません。そのため、加工やフィッティングの際にスピード重視で作業が進められることがあり、本来必要な工程が省略されることもあります。たとえば、ネジの締め付け確認や緩み止め、ナイロール糸の交換といった細かい作業が省かれるケースや、レンズのサイズ調整が甘かったり、フィッティングが不十分だったりすることもあります。また、出荷時の検品も簡易的で、細かい不備を見逃してしまう可能性が指摘されています。
一方、高価格帯の眼鏡店や専門店では、豊富な経験と高い技術力を持つスタッフが常駐していることが多く、丁寧なヒアリングを通じた視力測定や、顔の形状や瞳の位置に合わせた精密なフィッティングが行われています。特に、国家資格である一級眼鏡作製技能士が在籍している店舗では、専門的な知識に基づいた適切な提案が受けられるため、安心して任せることができます。加工の段階でも、ネジの確認や緩み止め処理、超音波洗浄といった細やかな工程が丁寧に行われ、完成度の高い仕上がりが期待できます。
また、視力測定においても、ベテランスタッフが対応することで、より正確な度数や適切な設計のレンズが選ばれます。特に、遠近両用眼鏡のように高度な調整や知識が必要な場合は、技術に優れた眼鏡店を選ぶことが重要になります。こうした従業員の知識と技術の差が、結果として眼鏡の価格や品質に反映されているのです。
このように、格安眼鏡チェーンとその他の眼鏡店では、ビジネスモデルから接客・加工技術、アフターケアに至るまで多くの違いが存在しています。価格の安さだけでなく、どのようなサービスを求めるのか、自分に合った眼鏡を長く快適に使うためにはどこで購入するのが適切かを、しっかりと考えることが大切です。
産地とブランドによる価格の違い
眼鏡の価格が高いか安いかは、単にお店の価格設定だけでなく、製造された産地やブランドの違いによっても大きく左右されます。ここでは、そうした「産地」と「ブランド」が価格にどのように影響しているのかを見ていきます。
産地の違い
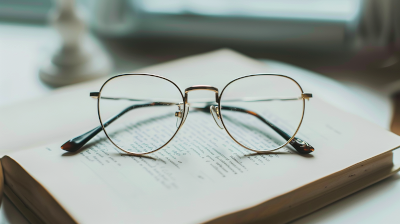
まず、眼鏡の価格に大きく関わるのが、どこで作られているかという「産地」の違いです。中国など海外の大規模工場で大量生産された眼鏡フレームは、生産コストが低いため非常に安価に提供されるのが一般的です。そのため、低価格帯の眼鏡の多くは中国製のフレームが採用されています。ただし、価格が安い一方で、耐久性や細やかなフィット感といった面で不安が残ることも指摘されています。
一方、イタリア製の眼鏡は、デザイン性に優れ、洗練されたスタイルが特徴です。イタリアはシャネルやグッチなど、世界的ブランドのライセンスを持つ工場も多く、ファッション性を重視する人に人気があります。デザイン料やブランド価値が加わるため、比較的高価な価格帯に位置しています。
さらに、日本製の眼鏡、とりわけ福井県鯖江市で作られるフレームは、世界でもトップレベルの品質を誇ります。鯖江は眼鏡づくりの街として知られ、長年にわたる職人の技術が受け継がれてきました。日本製のフレームは、耐久性や掛け心地へのこだわりが非常に高く、細部まで丁寧に作られているため価格も高めになる傾向があります。最近では、安い眼鏡にもチタン素材が使われることがありますが、鯖江製のフレームは、チタンを常温で複数回プレスするなど手間のかかる工程を経ることで、より強く錆びにくく仕上げられています。一方、海外製のチタンフレームは熱を加えて一度に成型するため、強度や精度にばらつきが出やすいといわれています。また、眼鏡市場も鯖江に自社工場を持ち、高品質な製品づくりと徹底した品質管理に力を入れています。このように、どこで作られた眼鏡かによって、価格と品質には大きな違いが生まれるのです。
ブランドの違い
眼鏡の価格は、ブランドの違いによっても大きく変わります。たとえば、シャネル、グッチ、オークリーといった有名ブランドのフレームは、ブランドそのものの価値や、デザインにかかるコストが上乗せされるため、どうしても高価になりがちです。こうしたブランド眼鏡は、ファッションの一部としても楽しむことができ、ブランドの持つイメージやステータスを重視する人たちに人気があります。高価格のブランド眼鏡を選ぶことで、デザインやブランド名がもたらす「特別感」を得られるという点も魅力です。
また、眼鏡店によっては、オリジナルブランドと他ブランドとのコラボレーション商品を展開していることもあります。こうしたコラボ商品は、デザイン性が高く、それでいて価格が抑えられていることが多いため、コストパフォーマンスの良さが魅力です。一方で、オリジナルブランドの商品は、ブランド料がかからない分、比較的リーズナブルな価格設定となっている場合もあります。特にブランドにこだわりがない場合は、オリジナルブランドの眼鏡を選ぶことで、価格を抑えつつ品質の良い眼鏡を手に入れることができます。
さらに、同じブランドでも、使われる素材や製造工程の違いによって価格が変わることもあります。たとえば、チタンやアセテートなどの高品質な素材を使ったフレームは価格が高くなり、より複雑な加工や手作業の工程が入ると、さらに価格は上がります。このように、ブランドと一口に言っても、その背景にはデザイン料、素材、製造コストといったさまざまな要素が絡んでおり、それらが価格に大きな影響を与えています。
眼鏡の価格を決める要素は、一見すると見えにくい部分も多くありますが、「どこで作られたか」「どのブランドか」を知ることで、その価格が高い理由、安い理由が見えてきます。価格だけで判断するのではなく、自分にとって必要な品質や価値を見極めて選ぶことが大切です。
レンズの種類と価格差
眼鏡の価格は、フレームだけでなくレンズの種類によっても大きく異なります。特に、レンズの設計や機能によって価格差が生まれる理由を理解することで、自分に合ったレンズ選びがしやすくなります。
単焦点レンズと多焦点レンズ(遠近両用・中近両用)の価格差
レンズには、大きく分けて単焦点レンズと多焦点レンズがあります。単焦点レンズは、遠くか近くのどちらか一点に焦点を合わせるシンプルなレンズで、価格も比較的安価です。一方、多焦点レンズは、遠くから近くまで複数の距離に対応できるように設計されたレンズで、遠近両用や中近両用といった種類があります。多焦点レンズは、度数が一枚のレンズの中で滑らかに変化するように設計されているため、製造に高度な技術が必要となり、価格が高くなりがちです。たとえば眼鏡市場では、単焦点レンズだけでなく、遠近両用などの多焦点レンズや超薄型レンズも一式価格に含まれている場合がありますが、一般的な市場価格では遠近両用レンズは2〜6万円台が相場とされています。
累進設計の複雑さと価格
遠近両用レンズは、上から下にかけて度数が変わる「累進設計」が採用されています。この設計によって、1枚のレンズで遠くも近くも見えるようになりますが、度数が滑らかに変化することでどうしてもレンズ収差(ユレやユガミ)が発生しやすくなります。高性能な遠近両用レンズほど、この収差を抑えるために非常に精密な設計がされており、より自然な見え方が実現されます。その分、製造工程も複雑になり、価格が高くなるのです。
オーダーメイドレンズによる自然な見え方の実現
近年では、より快適な視界を求める人のために、一人ひとりに合わせたオーダーメイドレンズも登場しています。これらのレンズは、単に度数に合わせるだけでなく、乱視の度合いや目とレンズの位置関係、瞳孔間距離、レンズの傾き、フレームの形状なども考慮して作られます。そのため、同じ度数のレンズでも、オーダーメイドならよりクリアで歪みの少ない見え方を実現できます。千里堂眼鏡のように、顧客のライフスタイルや使用目的まで分析し、オリジナルカスタマイズレンズを提案する店舗もあります。このようなオーダーメイドレンズは、価格が高めですが、その分だけ高精度な視界や自然な掛け心地を求める人には適しています。
機能性レンズ(ブルーライトカット、調光、偏光など)の追加料金
ブルーライトカットや調光(紫外線によって色が変わる)、偏光(まぶしさをカットする)といった機能を持つレンズも人気があります。ただし、こうした機能性レンズは通常のレンズにオプションとして追加されるため、別途料金がかかるのが一般的です。たとえば眼鏡市場では、傷防止やブルーライトカットなどのオプションを一式価格に3,300円(税込)追加することで選ぶことができます。ただし、安価なレンズにブルーライトカット機能がついている場合、反射が強かったり、レンズ自体に青みがかって見えることがあります。一方、価格が高いレンズでは透明度が高く、反射も抑えられているため、より自然な見え方が可能です。ただし、最近ではブルーライトカットが子供の近視進行に影響を与える可能性があるという意見もあり、特に子供用眼鏡では慎重に検討する必要があります。
レンズメーカーによる品質と価格の違い
レンズの価格と品質は、製造メーカーによっても大きく異なります。一般的に、ZEISS(ツァイス)やニコンといった有名メーカーのレンズは、設計技術や素材、コーティング技術が優れており、価格も高めです。これらのメーカーは、レンズの歪みの少なさや視界のクリアさ、耐久性などに定評があり、長く快適に使える品質を提供しています。また、オーダーメイドレンズの分野でも高性能な商品が揃っており、特に視界にこだわる人に支持されています。
一方で、安価なレンズは大量生産やコストカットによって低価格を実現している場合が多く、コーティングの耐久性やレンズの透明度、歪みの少なさといった点では差があることが指摘されています。ただし、度付きサングラスや予備の眼鏡、仕事用など用途を限定する場合には、コストを抑えたレンズでも十分に使えるケースもあります。
このように、レンズの種類、設計、機能、メーカーによる違いが、価格の差に直結しています。価格が高いレンズにはそれだけの理由があり、どのような視界や快適さを求めるかによって選ぶべきレンズも変わってきます。安さだけを重視するのではなく、自分の生活スタイルや用途に合ったレンズを選ぶことが、満足度の高い眼鏡選びにつながるでしょう。
チェーン店の眼鏡が安い理由とは?:選び方のポイント
- 安い眼鏡は目に悪い?
- 目に優しい眼鏡の選び方
- 高い眼鏡のメリット
- 眼鏡を選ぶ際に価格以外に重視すべきこと
- 通販で眼鏡を買うリスク
安い眼鏡は目に悪い?

最近では、低価格で購入できる眼鏡が数多く登場していますが、「安い眼鏡は本当に大丈夫なのか」「目に悪いのではないか」と不安に感じる人も少なくありません。結論から言えば、安い眼鏡が必ずしも目に悪いわけではありません。しかし、選び方を間違えると、目に負担をかけたり、本来の視力矯正の役割を十分に果たせない場合もあります。
視力測定の精度と度数の重要性
まず気をつけたいのが、視力測定の精度です。格安眼鏡店ではコスト削減のため、必ずしも十分な経験や資格を持つスタッフが測定を行っているとは限らず、その結果、正確な度数が得られないこともあります。多くの眼鏡店では「遠くがよく見える」ことを重視して度数を合わせることが一般的ですが、現代社会ではパソコンやスマートフォンなどの近くを見る作業が中心となっており、「遠くが見えやすい」眼鏡が必ずしも使いやすいとは限りません。ライフスタイルに合わない度数の眼鏡を使い続けると、目が疲れやすくなり、結果的に視力低下の原因となることもあります。そのため、一人ひとりの生活に合わせた度数を提案する千里堂眼鏡のような店舗もあり、「近くを見る負担を軽減する眼鏡」の提案も重要視されています。
フレームとレンズの品質による影響
次に考慮すべきは、フレームやレンズの品質です。安い眼鏡では、プラスチックや安価な合金などの素材が使われていることが多く、耐久性や柔軟性に欠ける場合があります。特にプラスチックフレームの場合、インジェクション成形という大量生産向けの方法で作られていることが多く、顔の形に合わせた細かい調整が難しい傾向があります。その結果、眼鏡がずれやすかったり、こめかみを圧迫したりして、掛け心地が悪くなることもあります。さらに、フレームの調整が不十分な場合、レンズの中心と瞳の位置が合わず、視界が歪む原因になることもあります。また、安価なレンズでは、傷防止やブルーライトカットといったコーティングの質が低かったり、レンズ自体に歪みが出やすかったりすることもあり、長時間の使用には適さないことがあります。
フィッティングの重要性
眼鏡の性能を最大限に発揮するためには、正しいフィッティングも欠かせません。度数が合っていても、眼鏡が顔にきちんと合っていなければ、快適に使うことができません。特に遠近両用眼鏡のような高度な設計のレンズでは、レンズの中心と瞳の位置がズレると大きな違和感を生じ、見え方にも悪影響を与えます。しかし、格安眼鏡店ではコスト削減のためにフィッティングの技術を持つスタッフが少なかったり、調整に十分な時間をかけられないこともあるため、満足のいく掛け心地が得られないことがあります。適切なフィッティングが行われていない眼鏡は、長時間かけていると頭痛や肩こり、眼精疲労といった体への負担にもつながるため注意が必要です。
安い眼鏡でも問題ないケース
とはいえ、すべての安い眼鏡が目に悪いわけではありません。たとえば、近視や遠視の度合いが軽い人や、室内限定の用途、サブ眼鏡として使う場合には、安価な眼鏡でも十分なこともあります。また、ZoffやJINSのような格安眼鏡チェーンでは、製造から販売までを一貫して行うSPA(製造小売)方式を採用しており、中間マージンを減らすことでコストを抑えながら、一定の品質を保っています。このため、予算を重視しつつ、ある程度の品質を求める人にとっては、こうした店舗も選択肢の一つになります。
自分に合った眼鏡選びの大切さ
結局のところ、価格にかかわらず大切なのは「自分の目の状態や使用目的に合った眼鏡を選ぶこと」です。特に、長時間眼鏡をかける人や、快適な見え方や掛け心地を重視したい人にとっては、丁寧な視力測定、質の高いフレームとレンズ、専門的なフィッティングを提供してくれる眼鏡店を選ぶことが重要です。特に初めて眼鏡を作る人や、度数が強い人、遠近両用眼鏡を検討している場合には、実店舗で専門スタッフのアドバイスを受けながら選ぶことをおすすめします。多少価格が高くなっても、自分に合った眼鏡を選ぶことで、目への負担を軽減し、長期的に快適な視生活を送ることができるからです。
安さだけを重視するのではなく、自分の目とライフスタイルに本当に合った眼鏡を選ぶことが、結果的に「目に優しい」選択につながります。
目に優しい眼鏡の選び方
従来の「遠くが良く見える」眼鏡の問題点
従来の多くの眼鏡店では、「遠くが良く見える」ことを基準に度数を合わせることが一般的です。この方法は、遠くの景色や標識などをはっきりと見るためには有効であり、運転や映画鑑賞といった遠方視が中心となる場面では適しています。しかし、すべての人にとって必ずしも最適な方法とは限りません。特に、近くのものを見る機会が多い人にとっては問題となることがあります。遠くが良く見えるように作られた眼鏡を使って近くのものを見ると、目がピント合わせをするために無理な調節を強いられ、結果として目の疲れや肩こり、頭痛といった不調を引き起こす原因になってしまうのです。一般的に視力1.0以上が見えるように作られる遠方用の眼鏡は、遠くを見る用途には適していますが、日常生活の中で多くの人が行う近距離作業には、必ずしも向いているとは言えません。
近くを見るときの目への負担
私たちの目は、もともと近くを見るときに最も大きな負担がかかる構造になっています。特にパソコンやスマートフォン、タブレットといったデジタルデバイスの使用時間が増えた現代社会では、長時間にわたる近距離作業が目に過剰な負担をかけています。そのため、目の筋肉が疲労しやすく、いわゆる眼精疲労をはじめとする目の不調を感じる人が増えています。こうした状況で「遠くが良く見える」ことを基準にした眼鏡を使用すると、近くを見るときの負担がさらに増し、「眼鏡をかけると近くが見えにくい」と感じる原因にもなります。特に、近くの作業を快適に行いたい人にとっては、この点を考慮せずに眼鏡を作ると、かえって生活の質を下げてしまうことにもつながります。
ライフスタイルに合わせた度数の選び方
眼鏡を選ぶ際に重要なのは、その人のライフスタイルに合わせた適切な度数を選ぶことです。たとえば、運転やスポーツをよく行う人にとっては、遠方の視力をしっかり矯正できる眼鏡が必要です。しかし、デスクワークが中心の人や読書、タブレットの使用が多い人が、同じような遠く重視の眼鏡を使ってしまうと、近距離を見るために無理にピントを合わせる必要があり、結果的に目への負担が増えてしまいます。
たとえば、トラックドライバーが日常的に見る「遠くの標識」と、オフィスで一日中パソコン画面を見ているデスクワーカーが注視する「目の前の書類や画面」では、求められる焦点の距離がまったく異なります。このように、どの距離でどんな作業をするかによって、最適な度数の眼鏡は違ってくるのです。そのため、自分のライフスタイルや日々の視線の距離に合わせた度数の眼鏡を選ぶことが、目の疲れを防ぎ、快適に過ごすためには欠かせません。
「よく見える」ことだけを基準にせず、「自分の生活の中でどの距離を見ることが多いのか」をしっかり考えることが、本当に目に優しい眼鏡選びにつながります。
高い眼鏡のメリット
安い眼鏡が広がる一方で、高い眼鏡には価格に見合うだけの価値があります。ここでは、高価格帯の眼鏡がなぜ選ばれるのか、その理由を改めて整理して紹介します。
高品質なフレームとレンズによる耐久性と快適性
高価な眼鏡は、チタンやアセテート、レアメタル、貴金属など、耐久性とデザイン性を兼ね備えた高品質な素材で作られていることが多く、精密な製造工程を経て丁寧に仕上げられています。特に日本製の眼鏡、なかでも福井県鯖江市で生産されるフレームは、世界的にも高く評価されており、職人の技術によって仕上げられた製品は長く使うことができます。また、アセテートのような天然由来の素材は、美しい光沢と透明感があり、顔の形に合わせて調整もしやすいのが特徴です。レンズにおいても、価格が高いほどコーティングの質が優れており、傷がつきにくく、長期間クリアな視界を維持できるなど、耐久性に優れた製品が選ばれています。
優れたフィッティングによるストレス軽減
高い眼鏡は、掛けたときの快適さが大きな魅力です。アセテートなど調整が可能な素材を使っているため、顔の形にぴったり合うように微調整ができ、長時間かけても痛くなりにくく、ずれにくいという利点があります。また、専門店では熟練のスタッフが一人ひとりの顔に合わせてフレームを調整してくれるため、より高いフィット感が得られます。これにより、眼鏡によるストレスを軽減し、快適に日常生活を送ることができます。
クリアな視界と目の疲れの軽減
高価格帯の眼鏡は、レンズの質にもこだわっています。歪みが少なく、クリアな視界を実現するために高品質な素材と設計が用いられており、目への負担が軽減されます。ピントがすばやく合いやすいレンズや、視線を動かしても自然に見える設計のレンズなどが用意されており、長時間の使用でも目が疲れにくいのが特徴です。オーダーメイドレンズであれば、目の状態やライフスタイルに合わせて一枚一枚設計されるため、より快適な視界が実現できます。例えば、千里堂眼鏡が提案する「近くを見る負担をやわらげる眼鏡」のように、パソコン作業や読書が多い人向けに最適な度数が設定されることで、眼精疲労の軽減にもつながります。
豊富なデザインとブランドによるファッション性
高価な眼鏡の魅力は、性能だけではありません。豊富なデザインと有名ブランドのフレームは、ファッションアイテムとしての価値も高く、自分らしいスタイルを演出できます。シャネルやグッチといったブランドの眼鏡は、ブランドの価値やデザイン性が反映され、素材や細部の仕上げにもこだわりが見られます。デザイン性と機能性を兼ね備えたフレームは、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活躍し、眼鏡を「ただの道具」ではなく「自分を表現する一部」として楽しむことができます。
専門知識を持つスタッフによる丁寧なサービスと安心感
高価格帯の眼鏡を扱う店には、豊富な専門知識と高い技術を持つスタッフがいることが多く、丁寧な視力測定やフレーム選び、レンズの提案など、きめ細かいサービスが受けられます。度数や用途に合わせた的確なアドバイスだけでなく、購入後の調整やメンテナンス、修理、保証といったアフターサービスも充実しているため、安心して長く使い続けることができます。特に初めて眼鏡を作る人や、度数が強い人、遠近両用眼鏡を必要とする人にとって、信頼できるスタッフのサポートは大きな安心材料です。
結果的な満足度の高さと長く使える可能性
高品質なフレームとレンズ、丁寧なサービス、快適な掛け心地によって、満足度の高い眼鏡が手に入ります。また、しっかりと作られた眼鏡は耐久性も高く、長期間使えるため、多少価格が高くても結果的にコストパフォーマンスが良くなる場合もあります。頻繁に安い眼鏡を買い替えるよりも、長く愛用できる高品質な眼鏡を選ぶ方が、目の健康や快適さの面でもメリットが大きいと言えるでしょう。
このように、高い眼鏡は単に視力を矯正するだけでなく、快適な視界、目の健康、ファッション性、安心感といったさまざまな価値を提供してくれます。安さだけでなく、自分のライフスタイルやニーズに合った本当に良い眼鏡を選ぶことが、結果的に満足度の高い買い物につながるのです。
眼鏡を選ぶ際に価格以外に重視すべきこと
眼鏡を選ぶとき、価格は確かに重要な要素ですが、それだけにとらわれてしまうと、自分に合わない眼鏡を選んでしまうこともあります。より快適で目に優しく、長く使える眼鏡を選ぶためには、価格以外にも多くのポイントを意識することが大切です。
フレームとレンズの素材と品質

まず注目したいのが、フレームとレンズの素材や品質です。安価な眼鏡には、ポリアミドやウルテム、TR90といった樹脂素材が使われ、インジェクション成形という大量生産方式で作られることが一般的です。これらの素材は軽量で弾力性があり、温度変化にも強いという利点がありますが、細かい調整が難しく、質感もやや安っぽく感じられることがあります。
一方、高価格帯の眼鏡にはアセテートのような天然由来の素材が使われ、透明感や高級感のある光沢、豊富な色柄が楽しめます。アセテートフレームは熱を加えることで細かい調整ができ、掛け心地の向上にもつながります。また、金属フレームでは、最近は安い眼鏡にもチタンが使われるようになりましたが、高価なチタンフレームは複数回のプレス加工など手間をかけて作られており、強度や耐久性に優れています。
レンズに関しても、安いものは歪みやすく、コーティングの耐久性も低い場合があります。それに対し、高品質なレンズは高性能な素材や設計が使われ、傷がつきにくく、クリアな視界を長く維持できるなど、機能性にも優れています。特にオーダーメイドレンズでは、個々の目に合わせた度数や設計がなされ、より快適な見え方が実現します。
販売店のスタッフの知識と技術力
良い眼鏡選びに欠かせないのが、販売店のスタッフの知識と技術力です。とくに視力測定やフィッティングは専門的な技術が求められるため、経験や資格を持つスタッフが対応するかどうかは非常に重要なポイントです。格安眼鏡店ではコスト削減のため、経験の浅いスタッフが対応することもあり、マニュアル通りの視力測定や雑な加工、調整が行われることもあります。
その一方で、千里堂眼鏡のように「一級眼鏡作製技能士」が在籍する店舗では、専門的な知識と高度な技術に基づいて、視力測定やフィッティングが行われます。こうした店舗では、一人ひとりの目や生活に合わせた適切な度数とフィット感が提供され、快適な眼鏡が作られます。視力測定は特に、豊富な経験を持つスタッフに対応してもらうことが望ましいです。
丁寧な視力測定と正確なフィッティング
快適な眼鏡には、丁寧な視力測定と正確なフィッティングが欠かせません。単に「遠くがよく見える」だけでなく、実際の生活に合わせた度数を選ぶことが大切です。特に、パソコンやスマートフォンを使う時間が長い現代では、「遠くが見える」ことだけを重視した度数では目が疲れやすくなることもあります。千里堂眼鏡のような店舗では、60〜120分かけたカウンセリングを通じて、目の使い方や生活習慣を詳しく分析し、最適な度数を提案しています。
また、フレームのフィッティングも重要です。レンズには「光学中心」と呼ばれる最もよく見える部分があり、それを正確に瞳の位置に合わせる必要があります。安価なインジェクション成形フレームでは調整が難しいことがありますが、アセテートやチタン製の高品質フレームは細かい調整が可能です。フィッティングが不適切な眼鏡は、ずれ落ちたり、痛みを引き起こしたり、視界が不安定になりやすいため、専門店での丁寧な調整が大切です。
アフターサービスの充実度
長く快適に眼鏡を使うためには、購入後のアフターサービスも重要です。フレームの歪みやネジの緩み、レンズの汚れなど、使っているうちにメンテナンスが必要になることは珍しくありません。一般的に、専門店では無料の調整やクリーニング、保証がしっかりしていることが多いですが、格安店ではアフターサービスが限定的だったり、修理が有料になることもあります。購入前に、どこまでのサービスが無料かを確認しておくと安心です。
自分のライフスタイルや目的に合った眼鏡選び
眼鏡は、使用する場面によって最適な度数やレンズが異なります。たとえば、運転やアウトドアなど遠くを見る機会が多い人と、デスクワークや読書が中心の人では、適した眼鏡が違います。パソコン作業が多い人が「遠く重視」の眼鏡を使うと、目の負担が増えかねません。千里堂眼鏡のように「どの距離が一番快適に見えたいか」を一緒に考え、ライフスタイルに合った提案をしてくれる店舗を選ぶと、自分に合う眼鏡に出会える可能性が高まります。
眼科医の受診をおすすめする理由
また、眼鏡を作る前に一度眼科医で目の状態を確認することも重要です。特に40歳以降や、最近視力に変化を感じる場合は、老眼だけでなく、緑内障や白内障などの疾患が隠れている可能性もあります。眼科での正確な検査と処方箋をもとに眼鏡を作ることで、安心して使える一本を選ぶことができます。強度近視の人も、目の病気のリスクが高いため、眼科受診が推奨されます。
子供用眼鏡の注意点
子供用の眼鏡を選ぶ際には、特に慎重さが求められます。最近注目されているブルーライトカットレンズも、子供の場合は近視の進行を防ぐために必要な光まで遮断してしまう可能性があるとして、むやみに選ばない方が良いという意見もあります。成長期の目に適切な眼鏡を選ぶためには、専門スタッフとよく相談し、慎重に決めることが大切です。
このように、眼鏡選びは価格だけでなく、素材や品質、スタッフの知識、視力測定とフィッティングの精度、アフターサービス、自分のライフスタイルや目の健康状態など、さまざまな視点から考える必要があります。価格だけにとらわれず、自分に本当に合った一本を選ぶことが、快適な視生活を送るための大切なポイントです。
通販で眼鏡を買うリスク
近年、手軽に利用できる通販サイトで眼鏡を購入する人が増えています。確かに価格が安く、デザインも豊富なため魅力的に映りますが、視力矯正が必要な眼鏡を通販で購入することにはさまざまなリスクが伴います。特に、長時間使用するための眼鏡や、度数の強い眼鏡を求める場合には、慎重に考える必要があります。
フィッティングと調整ができないリスク
眼鏡は度数が合っていればよいというものではありません。顔の形や目の位置に合わせてフレームを細かく調整する「フィッティング」がとても重要です。このフィッティングが適切に行われていないと、眼鏡がずれてきたり、圧迫感を感じたり、視界が安定しないなどの問題が生じます。結果として、長時間の使用が難しくなり、頭痛や肩こりといった体調不良につながることもあります。通販では実際に試着ができないため、こうしたフィッティングが一切行われません。また、安価なインジェクション成形のフレームは調整が難しいことが多く、通販で購入すると自分の顔に合わせることが困難になることも少なくありません。
視力測定が不十分なまま購入する危険性
眼鏡を作る際には、正確な視力測定が欠かせません。実店舗では、専門知識を持つスタッフが多様な検査機器を使い、現在の視力や乱視、左右のバランスを丁寧に測定したうえで、適切な度数を提案してくれます。しかし、通販では過去のデータや自己申告による度数情報をもとに注文することが多く、実際の目の状態に合っていない眼鏡が作られてしまう危険があります。特に初めて眼鏡を作る方や、度数が変わったばかりの方は、通販での自己判断によって誤った度数の眼鏡を作るリスクが高くなります。また、たとえ眼科医から処方箋をもらっていても、フィッティングが適切でなければレンズの中心と瞳の位置がずれてしまい、視力矯正効果が発揮されない場合もあります。
レンズ選びと加工の問題
レンズ選びも、専門的な知識がなければ難しい部分です。パソコン用、運転用、遠近両用といったさまざまな用途に合わせたレンズがありますが、通販では適切なレンズの選択について詳しく相談することができません。また、度数やレンズの種類に応じたフレームへの加工も重要ですが、通販ではそうした加工が簡略化される場合があり、レンズが外れやすくなったり、フレームが歪んだりすることもあります。特に、短時間で仕上げることを重視する場合、レンズが適切に固定されず、視界の安定性に問題が生じることもあるのです。
品質への不安
通販で売られている安価な眼鏡には、フレームやレンズの品質が低いものも含まれています。耐久性の低いフレームは折れやすく、レンズも歪みやすい場合があります。また、コーティングの質も低いため、傷がつきやすく、視界が悪くなることも考えられます。実店舗で扱う高品質な眼鏡は、耐久性のある素材と丁寧な製造工程で作られているため、長期間快適に使えるものが多いですが、通販の安価な製品ではその安心感が得られないこともあります。特に、調整が求められるプラスチックフレームは、アセテートなどのしっかりとした素材の方が掛け心地も良く、結果的に長持ちします。
アフターサービスの不十分さ
眼鏡は使っていくうちに、ネジが緩んだり、フレームが歪んだりといったトラブルがつきものです。実店舗で購入すれば、こうした調整や修理を無料で受けられる場合が多く、長く安心して使うことができます。しかし、通販で購入した眼鏡の場合、調整や修理を依頼するのが難しく、対応してもらえても有料になることが一般的です。特にフィッティングは、購入時だけでなく定期的なメンテナンスが必要なため、この点でも通販には大きな不安が残ります。
返品や交換が困難
通販では、届いた眼鏡がサイズやデザインが合わない場合でも、返品や交換が簡単にはできないことが多いです。特に度付きレンズの場合、原則として返品や交換ができないケースも多く見られます。また、返品の際に送料が自己負担になる場合もあり、気軽に交換や返金ができるとは限りません。その点、実店舗であれば事前に試着して確認できるため、こうしたトラブルを避けることができます。
処方箋が必要な眼鏡は実店舗での購入を
こうしたさまざまな理由から、特に視力矯正が必要な眼鏡は、通販ではなく実店舗で購入することが強く推奨されます。ファッション目的で度なしの眼鏡を購入する場合は通販も一つの選択肢ですが、度数が必要な眼鏡は慎重に選ぶべきです。特に初めて眼鏡を作る人や、度数が強い人、遠近両用レンズを希望する人などは、専門家のいる実店舗での丁寧な視力測定とフィッティングを受けたうえで選ぶことが重要です。眼科医の処方箋をもとに眼鏡を作る場合も、正しい位置でレンズを合わせるためのフィッティングが欠かせません。
眼鏡は目の健康に直結する大切な道具です。価格の安さだけにとらわれず、自分に合った眼鏡を安心して長く使うためには、やはり実店舗での購入が安心です。
チェーン店の眼鏡が安い理由と高い眼鏡との違い:まとめ
記事のポイントをまとめます。
- チェーン店の眼鏡が安い理由は製造から販売までのコスト削減にある
- 安い眼鏡はフレームやレンズの素材が低コストな場合が多い
- 高い眼鏡は高品質な素材と手間をかけた製造工程で作られている
- レンズの設計やコーティングによっても価格差が生まれる
- 安い眼鏡は視力測定やフィッティングが簡略化されることが多い
- 高い眼鏡店では専門スタッフによる丁寧な視力測定が行われる
- フィッティングの技術によって快適な掛け心地が大きく左右される
- アフターサービスが充実しているのは高価格帯の眼鏡店が多い
- 安い眼鏡店では調整や修理が有料になることもある
- 中国製と日本製のフレームでは品質や耐久性に差がある
- ブランド料が価格に影響するが、それに見合うデザイン性もある
- レンズの種類や設計の違いが価格と使いやすさに直結している
- 自分のライフスタイルに合わない眼鏡は目の負担になることがある
- 通販での購入は調整や視力測定ができないため注意が必要
- 価格だけでなく品質やサービスも含めた総合的な視点で選ぶべき